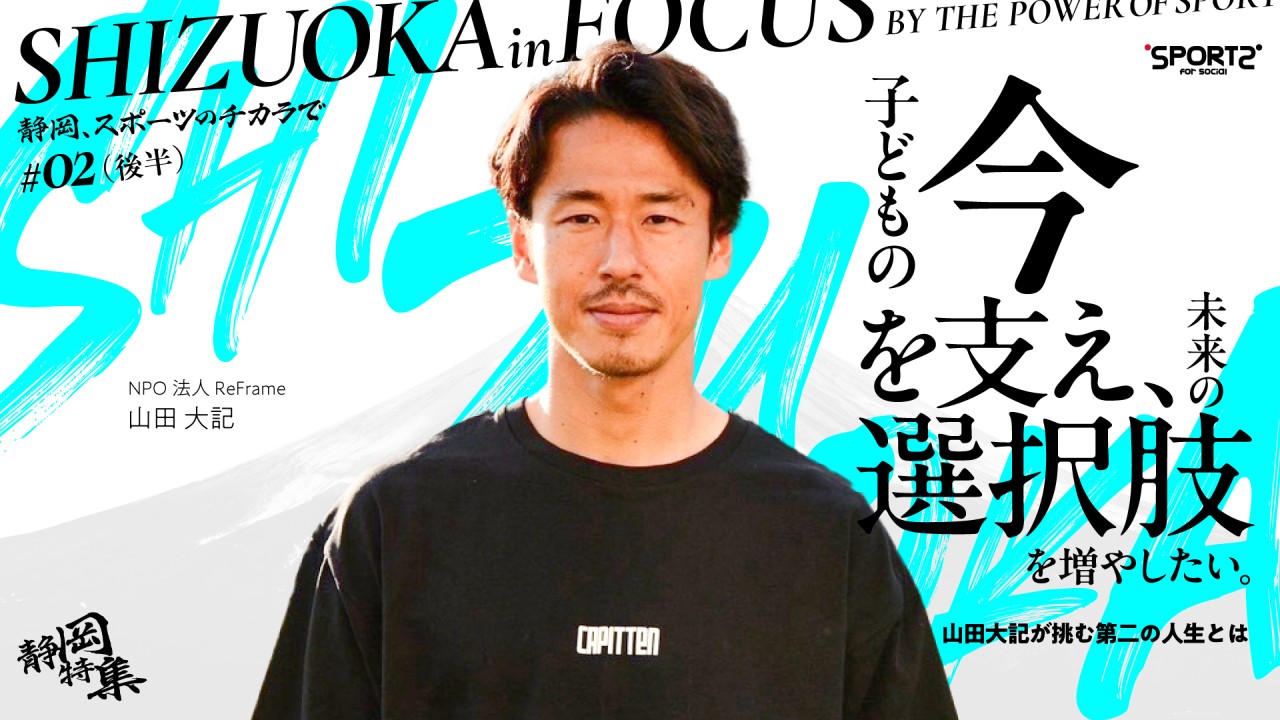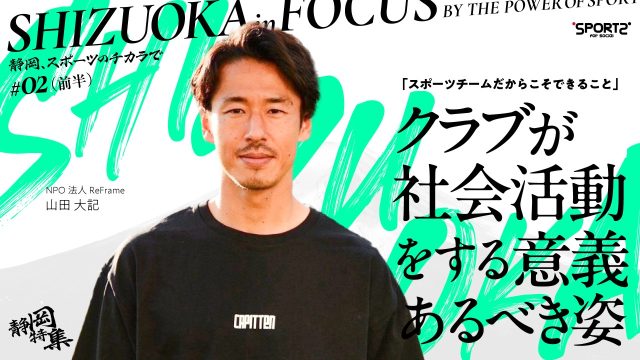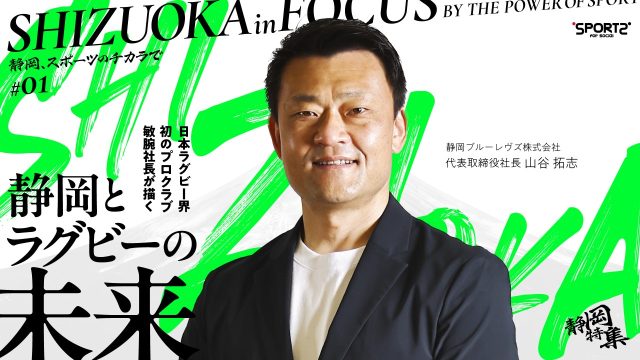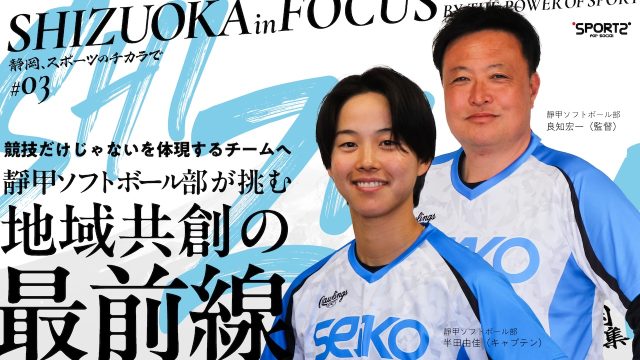「サッカー王国」として名を馳せてきた静岡。この地には、サッカーにとどまらず、9競技18チームものプロスポーツが存在し、地域とともに発展を続けている。
スポーツが持つ力で街を盛り上げ、社会をより良くする取り組みが活発に行われるこのエリア。スポーツと地域のつながり、そして静岡ならではの挑戦や未来への展望に迫る特集。スポーツ、静岡のチカラで。
静岡特集#02は『NPO法人ReFrame』副代表の山田大記さん。
前半の記事では、山田さんがこれまでプロサッカー選手として感じていたアスリートやクラブが行う社会的活動の意義と目指すべき活動の在り方について、後半は、元プロサッカー選手というキャリアから一転、生活困窮家庭の支援に力を入れ第二の人生を歩んでいる山田さんに、『NPO法人ReFrame』の活動内容や、その想いをお伺いしました。

「子どもたちを取り巻く本質的な課題にしっかりと目を向けて活動していこう」
ーー貧困の子どもに対する活動を積極的に行おうと思われたきっかけを教えてください。
山田)ドイツでプレーをしたときに、クラブや選手が当たり前のように地域の人たちの支援活動に取り組んでいる光景を目の当たりにして、サッカー選手として自分にも何かできることがあるかもしれないと思うようになりました。
日本への帰国後、児童養護施設への訪問や支援活動、試合への招待などを行うようになりましたが、そこで出会ったある男の子の一言が、活動を本格化させるきっかけになりました。その子は小学校3年生で、とてもサッカーが上手な子だったので、「プロサッカー選手を目指しているの?」と僕から声を掛けたのですが、「僕は施設にいるから、プロサッカー選手になる夢は諦めた。もうサッカーも辞めちゃったんだ。」という答えが返ってきました。小学3年生という、まだまだ夢を無邪気に語れるはずの年齢の子どもが、自分の置かれた環境を理由に、夢を諦めてしまっている。「自分には夢を追いかける資格がない」と子どもに思わせてしまう現実が、目の前にある。胸が締め付けられる思いがしました。
同時に、それまで僕たちが続けてきた5〜6年の活動が「どこか表面的なものだったんじゃないか」という大きな無力感にも襲われましたが、ともに活動している小川大貴(松本山雅FC所属)と話し合いを重ね、「子どもたちを取り巻く本質的な課題にしっかりと目を向けて活動していこう」と決意し、法人化して本格的に活動するようになりました。
ーーその経験から新たに芽生えた想いはありますか?
山田)「たとえ1人でも、僕たちの活動を通じて何かを感じてもらえたら」という想いを強くもって活動に取り組むようになりました。
僕たちがスポーツを通して実感してきたような、「夢を信じて頑張ることができた」「夢に向かって本気で挑戦したからこそ、大切なことを学べた」「かけがえのない仲間と出会えた」という経験に触れてほしい。だからこそ、環境を理由に夢を諦めてしまう子どもを、ひとりでも減らしたいと思っています。

“地域のみんなの居場所”をつくる子ども食堂や体験機会の提供を
ーー『NPO法人ReFrame』は具体的にはどのような活動をしているのでしょうか。
山田)現在は、月に1〜2回ほど、子ども食堂の開催やフードパントリー、体験機会の提供を中心に活動しています。
体験機会の提供は、できるだけ多くのことに触れられる機会を届けたいという想い、そして子どもたちの自己肯定感を育むことにもつなげたいという想いで活動しています。また、これらの活動では、子どもたちに直接関わることができるので、やりがいを感じる場面も多くあります。
みんなとても前向きな気持ちで参加してくれていて、「楽しかった!また来たい!」という声もたくさん届いています。子どもたちが楽しんでくれている姿を見ると、僕たちも元気をもらえる、そんなかけがえのない時間になっています。
ーーこども食堂は、“本当に必要としている”子どもたちが来ているのか?という点が度々話題にもなります。山田さんたちが実際に運営されていて、その点の実感はいかがですか?
山田)子ども食堂全体としてまだまだ“生活困窮家庭”へのリーチができておらず、活動に参加する人たちの中では多くて2割程度しかいないのが現状です。「いくつかのこども食堂を利用しています」という方がいらっしゃる一方で、1つの支援も受けてない方が大多数いることは、今一番解決したい課題であると感じています。
ーーその課題を解決するためにどのようなアプローチができるのでしょうか。
山田)一番変えていきたいのは、“イメージ”の部分です。たとえば『こども食堂』という言葉に対して、多くの人が持っているイメージが、本来の姿とは少しズレてしまっていると感じています。こども食堂は、本来“困っている人だけが行く場所”ではなく、誰でも気軽に来られる“地域みんなの居場所”です。
でも現実には、「経済的に厳しい家庭の子どもが行く場所」「ご飯が食べられない子が利用する場所」といった、限定的でネガティブなイメージが根強く残ってしまっています。こうしたイメージを変えていくためには、当事者である生活に困難を抱える方々の認識だけでなく、そうではない方々の認識も変えていく必要があります。
今のままだと「そういう場所に行くのは恥ずかしい」と感じてしまい、足を運びづらくなってしまうのではないかと危惧しています。一方で、「困っている子どもたちのために」という想いから、企業の方々に協賛いただき、寄付をいただいているという背景もたしかにあります。だからこそ、支援してくださる企業の皆さん、利用するご家庭、そして地域の方々、関わるすべての人たちのバランスを大切にしながら、これからのコンセプトを丁寧に設計していく必要があると感じています。
ーー子どもたちにとっても、地域の人たちが集う場所に行くことで、子ども同士や大人とのコミュニケーションも生まれるよい場所であることが大事なのですね。
山田)そうですね。集まった方々のコミュニケーションが生まれるようには僕たちも意識していますし、かなり活発に生まれています。ご家庭同士のコミュニケーションもありますし、あとは学習支援団体さんなどとコラボイベントをすることもあるので、たくさんの大人と関わる機会提供ができているのではないかと感じています。
いろいろな関わりが生まれることが、子どもたちの居場所作りにも繋がりますし、いろいろな大人と関わることで子どもの未来の選択肢を作るきっかけが生まれたらいいなと思っています。

“お金”という形で地域の支援活動を活性化させる『浜松こども基金』
ーー2025年に発表をされた『浜松こども基金』についても教えていただけますか?
山田)『浜松こども基金』は、地域の支援団体のお困りごとを解決していくことをミッションに活動している事業です。これは先ほどお伝えした活動とは少し異なり、自分たちが子どもたちに接することはなく、“お金”という形で地域の支援活動を活性化させ、活動の持続可能性を確保するためのものです。“中間支援”とも呼ばれるこうした役割は、支援の輪を広げていくうえでとても重要なポジションだと考えています。
ーーどのような背景から、こうした中間支援の活動を始めたのでしょうか?
山田)この事業を始めた背景には、支援団体やNPOの皆さんの活動が本当に素晴らしい一方で、資金面の課題によってどうしても活動の幅に限界があるという現実を知ったことがあります。実際、この浜松周辺の地域だけでも、さまざまな制約の中で思うように動けずにいる方々がたくさんいらっしゃいます。
そこで、僕たちが助成金という形で、そうした団体の活動を後押しする“中間支援”の仕組みをつくれば、より多くの人たちに支援が届くのではないかと考えるようになりました。僕自身、実際に活動されている方々の強い想いや姿勢に、たくさん影響を受けてきたので、こうした中間支援にもこれからしっかりとコミットしていきたいと思っています。
ーー『浜松こども基金』に協力したいと感じられた企業は、どのようなプロセスで寄付をすることができるのでしょうか?
山田)こども基金は、来年に向けて現在発起人を集めています。個人で1万円を寄付したら発起人になれるという仕組みなので、まずは経営者の方にも個人で入ってもらっています。目標は1,000人=1,000万です。地域みんなで力を合わせて子どもたちのために作る基金にしたいので、多くの方にご協力をいただけるよう活動していきます。

助け合いや繋がりで“当たり前に支え合える”社会へ
ーー山田さん自身は、こうした活動を通してどのような社会になれば良いと考えていますか?
山田)僕たちが取り組んでいる“貧困”という社会課題も、地域の中での助け合いやつながりによって解決していけるものだと思っています。また、支援の現場ではどうしても「支援する側」「支援される側」という上下の関係性が生まれやすいですが、僕たちはそうではなく、横並びの関係でありたいと考えています。
「自分は誰かに助けてもらわなきゃ生きていけない存在なんだ」と感じてほしくありません。人間社会は本来、“困ったときはお互い様”なものですよね。昔は、それがもっと当たり前だったように思います。
じゃあ、なぜそれが難しくなってしまったのか。
きっと、僕たちの心の温かさがなくなったわけではなくて、社会の構造が変化し、SNSの普及などでご近所同士の関係性やつながりのあり方が変わってしまっただけなんだと思います。でも、人を思いやる気持ちは、誰の心の中にもちゃんと残っています。だからこそ、当たり前に支え合える社会やそのための仕組みを、これからも僕たちは積極的につくっていきたいと考えています。
ーーありがとうございました。




写真提供:NPO法人 ReFrame