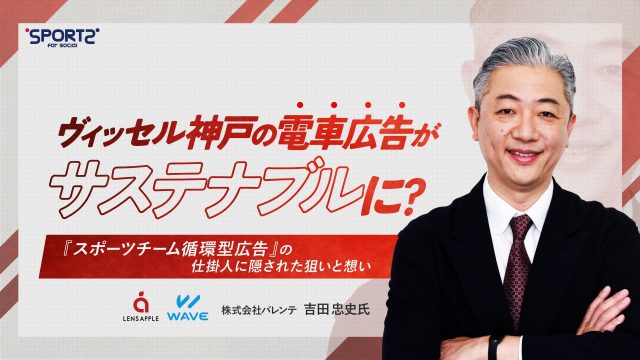「障がいのある子どもが、スポーツをする場所がない──」
そんな保護者の声をきっかけに、東京ヴェルディの中村一昭コーチ(以下、中村)は、障がいのある方たちのスポーツの現場づくりに奔走してきました。現在は、Jリーグクラブ初の『障がい者スポーツ専門コーチ』として活動しています。
「障がいのある方のスポーツの場を増やす」「障がいに対する理解を広める」「障がいの有無に関わらず一緒に楽しむ」という3つの柱を軸に、都内各地で活動を展開する東京ヴェルディ。行政や企業と連携した障がい当事者向けのスポーツ教室や、特別支援学校の訪問など、その年間活動回数は300に迫るほどですが、どんなにいい取り組みでも、実践する担い手=“仲間”がいなければ、社会全体に広がってはいきません。
その課題を打破すべく東京ヴェルディがスタートさせるのが『障がい者スポーツ事業立ち上げ講習』です。その第1回となる株式会社フクシ・エンタープライズとの講習会が行われました。「障がいがあるからできない」を地域からなくすことを目指した想いの共有と実践的ノウハウの伝達について、中村コーチに想いを伺いました。

“仲間”を増やすための障がい者スポーツ事業立ち上げ講習会
ーー中村コーチが『障がい者スポーツ事業立ち上げ講習』を始めようと思ったきっかけを教えてください。
中村)東京都内で障がいのある人たちがスポーツをできる環境を整える活動を始めて10年になり、多くの方々に広がってきたことを実感しています。
同時に、これを全国に広げていくことは、とても時間がかかることだとも感じています。私が生きているうちに、日本中で障がいのある人が気軽にスポーツを楽しめる世界を見たい。けれど、今のままのスピードでは、それは到底間に合いません。実現のためには、東京を中心に地道に活動を行いながらも、私たちが積み重ねてきたノウハウを共有することで“仲間“が増え、障がいのある人たちがスポーツをできる環境が増えてくることが必要不可欠です。
実は、他のJリーグクラブやスポーツ団体からの問い合わせも増えているんです。「どのような活動をすればよいか」「障がいのある方に対してどのような配慮が必要か」など、東京ヴェルディの活動について聞かれることが多くなってきました。そのこともきっかけになりました。
Jリーグのクラブだけではなく、野球、テニス、バスケ、ラグビーなどのスポーツチーム、学校や企業、指定管理団体など、スポーツに関わるさまざまな方々を対象にこの活動を届けたいと思って講習をスタートさせました。
ーー“仲間を増やす”ということに強い想いを感じます。
中村)インクルーシブをテーマにした活動やイベントも、その場が成功して「よかったね」だけで終わりたくなくて。活動を日本中のいろいろな方に知ってもらって広がっていき、同じ目標を持って取り組む“仲間”になってくれたら嬉しいですよね。
今回の講習でも、こちらから教えて終わりではなく、受講者とはその後もなるべく多くコミュニケーションを取り、疑問や難しいことがあれば相談にも乗りたいと思っています。私も今まで関わってきた人たちによく相談をしましたし、その相手が増えることはとても大事なことです。
ーー中村コーチ自身も、ヨーロッパでの障がい者のスポーツ環境を視察しにオランダに学びに行くなど積極的に外部との関わりを増やす行動をしている印象です。
中村)学びに行くことで気づくことも多くありますよね。障がい者スポーツの活動を通して知り合った国際パラリンピック委員会元理事のリタ・ファン・ドリエルさんという方がいらっしゃって、彼女の勧めで2024年9月にロッテルダムを訪問し、現地での研修ツアーに参加しました。
例えば、オランダには『スポーツコンシェルジュ』という立場の人がいます。施設に障がいのある方が来たときに、「こんなスポーツが合ってるよ」とか「こんなことができるよ」とアイデアを出すような役割の人なのですが、私のような“指導者”でなくても、こうした立場の人がこの講習を通して増えることもいいことだなと思っています。そうしたことは私自身も“仲間”から学んだことです。

スポーツに参加できる場を増やす
ーー今回の講習会では、障がいがある状態を疑似体験しながら指導実践の時間をとり、指導する側、受ける側の両方を体験できる時間になっていました。
中村)この講習会では、大人数の活動や知的障がいや精神障がいを含めいろいろな障がいのある人が混ざった中での活動において、どうリスクマネジメントをしているのか、どのように工夫したら参加者に楽しんでいただけるのか、というアイデアを、実際に現場で見て、経験して、それを持ち帰ってもらうようにしています。今回は講習会の中での体験でしたが、実際に東京ヴェルディが行っている活動の見学も含めて“体感する機会”を作るようにしています。

ーー講習会に参加された方が、どのような“体感”をすることを期待していますか?
中村)もしかしたら、スポーツの指導をする方々の中には「自分はスポーツの指導者だから、障がいのある人は関係ない」と思っている人も多いかもしれません。
ですが、どの地域にも障がいのある人は必ずいます。この講習で体感したことが障がいのある人たちを受け入れる準備に繋がり、「どうせこのチームには入れてもらえないだろう」ではなく、「ここならスポーツを楽しめる」と思ってもらえるような団体になっていってくれると嬉しいですね。
ーー指導者がこういった講習会を受けている、というチームはまだ少ないのでしょうか。
中村)「障がいのある人たちの活動はリスクがある」「怪我をさせてしまったらどうしよう」というイメージを持たれている話をよく聞きます。実際、そうしたリスクは障がいがあってもなくても変わらずあることですよね。
スポーツ団体側の気持ちもわかりますが、リスクが怖いから“できない”、“受け入れられない”という状況は非常に悲しい状況です。チームやクラブ側に、障がいのある方も受け入れる準備ができていることが大切です。一歩踏み出すきっかけを作るために、講習会を通して考え、自身で体験してみていただきたいですね。

障がいがあってもなくても変わらずスポーツを楽しむこと
ーー今回講習会を行ったフクシ・エンタープライズさんは、どのような課題を持っていたのでしょうか?
中村)フクシ・エンタープライズさんが管理している日野市の南平体育館で東京ヴェルディのインクルーシブスポーツイベントや障がい者スポーツ教室がはじまったことがきっかけで今回の講習会が実現しました。さまざまな施設を管理しているフクシ・エンタープライズさんは、インクルーシブな活動にも積極的ですが、より力を入れていきたいという想いや、資格を持っていても実践する場面がまだ少ないという課題もあったと聞いています。
ーー職員のなかに“インクルーシブ”な取り組みにやる気があっても、実践の場が少ないと不安にはなることもありますよね。
中村)実際にインクルーシブなイベントに参加し、一緒にスポーツをすると「障がいがあってもなくても変わらない」ということを知っていただけると思います。いろいろな現場に行き、いいところを学びながらさらにいいものを作っていく。こうしたきっかけにこの講習会がなるといいですね。
ーー中村コーチにとって、この活動がどう広がっていくことが理想ですか?
中村)Jリーグの全60クラブがインクルーシブな活動をすることで、「障がいがあっても一緒にスポーツを楽しめる」環境が、全国にスピード感をもって広がっていくと思っています。そのくらいJリーグクラブの地域への影響力は大きいですし、サッカー以外のスポーツでも、私たちが今まで培ってきたことをお伝えすることで「インクルーシブな活動をやってみよう」というスポーツ団体、学校、企業、自治体が出てくれば嬉しいです。
ーーこうした活動に意義を感じている一方で、クラブ単体、施設単体での活動を継続していくことも難しさがあるのではないかと感じます。
中村)オランダでは、こうした活動にサッカークラブだけが自前の資金を使うのではなく、自治体や企業のバックアップが大きくあると聞きました。企業・自治体・スポーツ団体の三角形をうまく使い、持続可能な活動にしているのは素晴らしいことです。
また、こうした活動の継続にはボランティアさんの活躍も見逃せません。エクセルシオールというチームでは、ボランティアさんが100人もいて積極的に活動しています。この方々は、「自分の成長のため」「困ってる人を助けたい」という想いがあってボランティアに参加しており、東京ヴェルディでもスポーツボランティアを立ち上げた際には高校生や若い方が同じような理由で参加してくれていました。

井戸端会議からつながる未来のやさしいまちづくり
ーーさまざまな立場から関わり、障がいのある人たちがスポーツをできる環境が作られていくことが理想ですね。
中村)スポーツの環境づくりだけでなく、最終的には“居場所づくり”にもつながると考えています。週1回または月1回、人と会うことで孤独感のカバーができる、そんな“井戸端会議”の場を全国に作れたら、みんなが安心して、寂しくなく、優しい社会を作っていけるのではないでしょうか。
ーーとくに障がいのある方、その家族の居場所づくりは大事ですよね。
中村)障がいのある人たちのための場になるとともに、誰もがその活動に参加できるようにすることによって、障がいのある人たちのサポートをしたいという想いを生むきっかけにもなり得ます。子どもたちには、障がいのある人たちのことを低年齢のうちから知る場にもなります。
私たちも仲間を増やし、全国にそうした居場所がある状態を作れるように活動していきたいです。東京ヴェルディの『障がい者スポーツ事業立ち上げ講習会』に興味を持たれたスポーツ団体や企業の方がいらっしゃれば、ぜひご連絡をいただきたいです。一緒に活動の輪を広げていきましょう!
ーーありがとうございました。
東京ヴェルディ障がい者スポーツ講習会の様子
 今では50人もの人数が集まる障がい者スポーツ教室も、2015年のスタート当時は5人しか集まりませんでした。「東京ヴェルディに対する信頼がない」「信頼がないと子どもを参加させられない」という厳しい言葉を投げかけられながら、福祉作業所との熱心なコミュニケーション、地域の巻き込みを行いながらここまでこの事業を広げてきたその過程を包み隠さずに伝えていきます。
今では50人もの人数が集まる障がい者スポーツ教室も、2015年のスタート当時は5人しか集まりませんでした。「東京ヴェルディに対する信頼がない」「信頼がないと子どもを参加させられない」という厳しい言葉を投げかけられながら、福祉作業所との熱心なコミュニケーション、地域の巻き込みを行いながらここまでこの事業を広げてきたその過程を包み隠さずに伝えていきます。

それぞれが指導者、視覚障がい者、車いす使用者に分かれながら、実際の体験会の様子を再現。さまざまな障がいの方がいる環境で、どのような気配りをするのかを体験します。
講習会に関心のある企業、行政、教育機関、スポーツ団体の方はこちらより詳細をご確認ください。
東京ヴェルディ公式サイト:https://www.verdy.co.jp/news/14366