「誰にも我慢させない、優しい空間にしたい。」
これは、いわきの子どもたちが新しいスタジアムに寄せた願いです。
そして今、その言葉が現実のものになろうとしています。クラブとサポーターが手を取り合い、誰もが安心して観戦できるスタジアムづくりに取り組み始めました。いわきFCは2025年、Jクラブとして初めて「DLT(Disability Liaison Team)」を設置しました。障がいのある方とクラブをつなぐ“橋渡し役”としての新たな仕組みです。さらに「DSA(障がいのあるサポーター団体)」も立ち上がり、当事者同士のつながりや声の共有が生まれています。
この取り組みの根底にあるのは、「誰ひとり取り残さないスタジアムをつくる」という強い思いです。特別扱いではなく、必要な配慮を自然に実現していく。クラブとサポーターが対話を重ね、ともに工夫しながら、すべての人が「また行きたい」と思えるスタジアムの実現を目指しています。
小さな声が、大きな変化を生む。いわきの地から、そんな希望のモデルが生まれようとしています。
インタビュー対象
- 一般社団法人VER Sports Base 代表 宇野奈穗さん
- 株式会社いわきスポーツクラブ(Jリーグ いわきFC)川﨑渉さん
- 株式会社いわきスポーツクラブ(Jリーグ いわきFC)岩崎優奈さん

「見えなかった景色」から始まった気づき
ーーまず、宇野さんがいわきFCさんと関わりをもったきっかけを教えていただけますか。
VER Sports Base 宇野)2023年の7月に、いわきFCのマスコットキャラクターである『ハーマー&ドリー』に会いにいわきグリーンフィールド(現:ハワイアンズスタジアムいわき)へ観戦に訪れたことが最初の関わりでした。介助者に加えて友人とも3人で一緒に観戦できる席が取れたので、すごく楽しみにしていたのですが、車いす席の目の前にある柵と通路の人通りのために、ピッチ上の選手やボールがとても見づらい席でした。
試合後「これは車いす利用者にとって良い環境なのか?」という疑問をnoteに投稿すると、その日のうちにいわきFCの大倉社長から「なんとかします」といった旨のメッセージをいただきました。
いわきFC 川﨑)当時、私もその宇野さんからの発信を拝見しました。実は、“柵や通路の人通りが車いす席利用者の方の視界を遮っている”という問題はクラブとして認識はしていたものの、施設上の問題のため改善することが難しいと考えていました。
しかし、宇野さんの発信を受け、改めて運営担当を中心に車いす席の視野改善について話し合いました。さまざまな方法を考え、1週間ほど議論を重ねたときに、社長の大倉からふと「ピッチサイドにスペースを作ればいいのでは」と提案があり、すぐにピッチサイドの車いす席導入に至りました。
宇野)その「ピッチサイドに車いす席が設置され、試験運用が行われる」ということは、いわきFCのサポーターの方から知りました。「こんなに早く対応してくださることなんてあるんだ」ととても驚きましたね。
ーー導入までのスピード感が素晴らしいですね。
川﨑)J2に昇格したばかりで急激に来場者が増えたシーズンで、車いす席のお話だけでなく、お客様の声で課題に気づき、改善していった点がいくつもありました。その「お客様の声を拾って改善をしていこう」というスタンスは今も変わりませんが、当時はクラブ全体がより敏感でしたね。
宇野)「ハード面の問題なので解決が難しい」と、改善に関する議論を止められてしまうことは往々にしてあることなのですが、いわきFCさんは、視点を変えながら何か対応できないか考えてくださり、その姿勢が本当にありがたいです。
今回、私が一般社団法人VER Sports Baseを立ち上げるにあたって、一番最初にお話をするならどこかと考えたときにいわきFCさんがすぐに思い浮かぶほど、その積極的な姿勢には信頼を寄せています。
 いわきFC ピッチサイド車いすエリア
いわきFC ピッチサイド車いすエリア“対話するクラブ”が選んだ、DLTとDSAという仕組み
ーー先日、いわきFCさんがJリーグクラブで初めてDSA(Disabled Supporters Association)とDLT(Disability Liaison Team)を設置されました。まずは宇野さんから改めて、DLTとDSAについて教えてください。
宇野)DSAは障がいのあるサポーター自身のコミュニティです。障がいのあるサポーターの声を集め、代表してバリアフリー関連の問題などをクラブと定期的に話し合います。
DLTは、クラブと障がいのあるサポーターの橋渡しをする役割を担います。プレミアリーグではDLO(Disability Liaison Officer)と呼ばれることが多いのですが、いわきFCさんはチームでやられているので、DLTになっています。
ーー岩崎さんはDLTやDSAのこと、ご存じでしたか?
いわきFC 岩崎)正直、宇野さんから「イングランド・プレミアリーグではこんな取り組みがされている」とご提案いただくまではまったく知りませんでした。
これまでも障がいのある方から問い合わせをいただくことが多々あったので、このような仕組みがあれば、よりサポーターの方が相談しやすくなったり、我々が見えていない問題を拾いやすくなったりするのではないかと思い、社内に持ち帰ったところ、すぐに社長の大倉まであがり「やろうよ」という話になりました。

ーー宇野さん、いわきFCのDLT・DSAという存在の意義についてはどうお考えですか。
宇野)現状、障がいのあるサポーターがスタジアムで不便を感じたときに、クラブに相談や問い合わせをする方法がメールしかなく、そのハードルから諦めてしまうこともよくある話です。しかし、DLTが「障がいのあるサポーターのための窓口」として存在することで、スタジアム観戦における不安や疑問を尋ねやすくなり、安心感に繋がると考えます。
クラブ側も、障がいのある方からの問い合わせにどう対応していいのかわからない、誰に相談すれば良いのかわからないということもあると思いますが、サポーターたちのDSAがあることで、障がいのある方ご本人やご家族の方に、クラブの対応やスタジアム環境のフィードバックを気軽に聞く関係性をつくれると思います。
ーーDSA立ち上げについて、サポーターの方々の反応で何か印象的なものはありますか?
宇野)いわきFCの『ムキムキDSA』に関しては、主となってくださっているご夫婦が、車いす席を利用している方や高齢者の方に「DSAという団体を作ります」と声をかけてメンバーを募ったのが始まりでした。今まで、車いす席を利用するサポーター同士でも顔見知り程度の関係性であったのが、DSAのメンバーとして1つのつながりができているように感じます。
DSAに所属することで、障がいのあるメンバー同士で相談し合うこともできますし、他の障がいの方が直面するバリアを共有・理解できることも、DSAの魅力の1つだと思っています。
ワークショップが生んだ“共創”の風景
ーーここからは先日行われたワークショップのお話をお伺いします。ワークショップ開催に至ったきっかけから当日の内容を教えていただけますか。
川﨑)クラブとして「国内初」をうたってDLT設置のリリースを出すことにはなったのですが、実際に今後何を行っていくのかが見えにくいので、目に見えるかたちで動きがあった方がいいと思いました。その中で、広報担当のアイデアで一度実際にDSAメンバーの方や、サポーターの皆さんと意見交換をする場を作ることを思いつき、メディアの方々もお呼びして先日のワークショップ開催に至りました。
岩崎)ワークショップ当日は20名の方にご参加いただき、3グループに分けてグループワークを行いました。今回は初回だったので、いわきFCのファンクラブ会員を対象に募集をしたところ、シーズンチケットをご購入いただいている方々、車いすをご利用の方が4組と、ご家族が障がいをお持ちの方、福祉事業に関わっている方などにご参加いただきました。
ワークショップではまず、今のハワイアンズスタジアムいわきでの課題や、こんなサービスあったらいいなといった意見を、グループごと机に置かれたスタジアムマップに付箋で貼ってもらい、出た意見を全体で共有しました。その後、新しいスタジアムの図を使って、新しいスタジアムにはこんな施設やサービスがあったらいいなというアイデアを、皆さんにたくさん出していただきました。

ーー実際にワークショップを行い、改めてクラブ側で気づきになったことや印象に残っていることがあれば教えてください。
岩崎)募集の際に参加者の方に書いていただいた、今回ワークショップに参加した理由のいくつかが印象に残っています。例えば、「家族に障がいのある方がおり、自身は試合に訪れているが、家族はスタジアムに来たことがなく、家族みんなで行ってみたい」という方がいらっしゃいました。そういったサポーターの方々の背景は、おそらくこのDLTのワークショップを開催しなければ私たちも知ることができなかっただろうと思います。
川﨑)私としては、障がいのない方もこのワークショップに参加されてたことがすごく印象的でした。バリアフリーやユニバーサルデザインという言葉がありますが、障がいのある方も障がい当事者以外の方も一緒に考えながら作っていくものなんだろうなと、このワークショップを通じて感じました。
岩崎)障がいのあるなしに関係なく「みんなが過ごしやすいスタジアム」を、参加者の皆さんと明るい雰囲気の中で考えることができたことで、今後この活動をさらに明るく広くやっていけるのではと可能性を感じました。
川崎)おそらく「こういうところが不便だ、こうしてほしい」という要望を受けて対応するだけの関係だと、根本の解決にはならないと思います。スタジアムに来る全員が、誰もが楽しめる観戦環境を一緒に作っていくことを理解している、そんな雰囲気が必要なのかなと感じましたね。
ーー宇野さんから見て、ワークショップの印象はいかがでしたか。
宇野)参加された皆さんが積極的に意見交換をされていて、「いわきFCのことがすごく好きで、より良いクラブになってほしい」という想いが強く伝わってくるワークショップでした。いわきFCさんのスタッフの方もサポーターの方も皆さんが、当事者意識をもって「良い観戦環境」を作り上げていくという意識が本当に素晴らしいなと思います。

また来たい」と思えるスタジアムを目指して
ーーいわきFCとして、DLTやDSAが始動したばかりですが、これから先、クラブとしてどうなっていきたいというのは何かありますか。
川﨑)今まさに我々は、クラブとして新しいスタジアム建設の計画を進めているところです。計画にあたり、市民の方々やサポーターの方々の意見はもちろんのこと、子どもたちの意見をかなり大事にしているのですが、子どもたちがまとめた「スタジアムに求める提言」の中に、「誰にも我慢させない居心地がいい優しい空間」というものがありました。そんなスタジアムを作っていくために、先日のワークショップのような意見交換会は定期的に行い、DLT・DSAの枠組みで得られた意見や発想を新スタジアムづくりに反映していきたいと思っています。
岩崎)私も、ワークショップは今後定期的に行っていきたいと考えています。普段、試合の運営を担当しており、対話できる関係性を大事にしていきたいので、ワークショップのような場以外でも、気軽に連絡を取り合いながら相談し合える関係性を継続していきたいです。
川﨑)加えて実は、海外のクラブのウェブサイトを参考に、障がいのある方が試合観戦を楽しむために必要な情報を一つにまとめたページを公式サイトにつくることを計画中です。少し時間はかかるかもしれませんが、情報提供はしっかり行っていきたいですし、ワークショップなどでどんな話し合いがされたかも、広く公開して見える形にしたいと思っています。
宇野)対話の場を作ることもそうですが、その情報提供も本当に大切だと思います。とくに障がいのある方にとって試合観戦は、下調べや手配をしてやっとその一日にたどり着くという過程があり、準備段階で情報の不十分さから観戦自体を諦めてしまう方もいます。もしクラブの公式サイトの中ですべての情報が1つにまとまっていたら本当に楽ですし、今まで観戦を諦めていた方が少しでも行ってみようかなと思ってくださるような、そして安心して観戦できるようになっていけばいいなと思いました。
ーーVER Sports Baseの立場として、宇野さんは今後のいわきFCさんにどのようなことを期待されていますか?
宇野)まずは何か課題点が見つかった時に、それをクラブだけで解決するのではなく、DSAの方々と協力をしながら解決していくアプローチを期待しています。また、いわきFCさんの課題解決までの迅速さや行動力もずっと変わらずいてほしいなと感じています。
新スタジアムに関しては、障がいのある方だけでなく、子ども連れの方、高齢者の方々などすべての層に優しいスタジアムを目指していると思います。それにはユニバーサルデザインが鍵になってくると思うので、私たちの視点での他のスタジアムの情報を共有したり、一緒に視察して考えたりしていきたいです。

ーー宇野さんは、どうしたらこのDLT・DSAの仕組みや活動が全国に広がっていくとお考えですか。
宇野)混同されやすい「特別扱い」という言葉と「合理的配慮」の違いなど、障がいについて理解を深めていくことが第一だと思います。先日のワークショップでも、障がいの「医学モデル」と「社会モデル」という2つの考え方についてお話をしましたが、そういった考え方や認識の共有を、各クラブとしていくことの必要性を感じています。
また、いわきFCさんを皮切りに、Jリーグ内や広くスポーツ界で共有できるモデルケースを作っていかなければならないとも思っています。「こんな問題を、DLTとDSAでこうやって解決した。」という好事例を作り、「こんなシステムがあった方がたしかに楽だよね」と実感していただくことが普及に繋がると考えています。
ーー最後に、いわきFCのお二人から見て、Jリーグ、そして日本のスポーツ全体で、いわきFCさんのような取り組みを広げていくために何ができると思いますか。
岩崎)実際にDLT・DSA導入のリリースを見て、とあるクラブから「障がいのあるサポーターへの対応に悩んでいることがあって相談したい」という連絡がありました。クラブ側としては、当事者の方に相談して一緒に解決していくという発想が今までなかったと思うのですが、ワークショップを通した対話の場づくりなど、私たちの事例を皆さんにも真似していただけたら嬉しいです。
川﨑)正直、私たちのようなクラブが、他のクラブはこうした方がいいと言うのは大変おこがましいのですが、DLT・DSAを導入することで対話の場のための仕組みを作れることは知ってほしいですね。どうしても大きいクラブになればなるほど、一人ひとりのサポーターの方の声を聞いていると収拾がつかなくなったり、1人のお客様だけを特別扱いできないという問題が出てくると思います。ただ、DLTという窓口をクラブ側に設け、当事者団体であるDSAともに改善していくという仕組みは、クラブが抱えるそういった難しさに対して一つの解決策になり得るのではないかと思います。
ーーありがとうございました! 




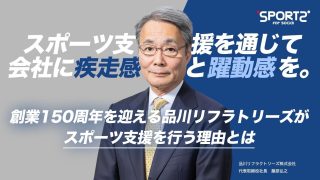
ー







