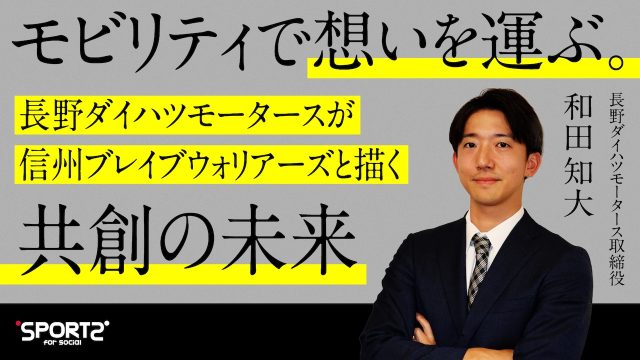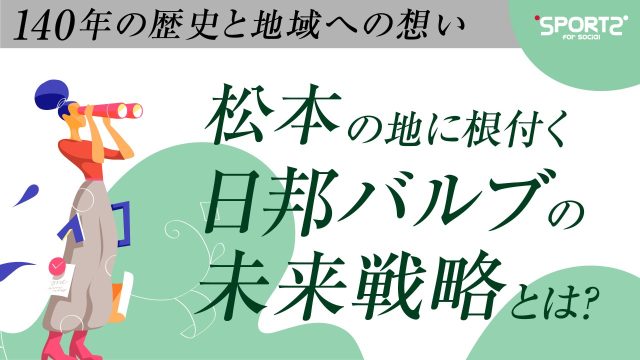長野県と新潟県の県境に広がる信越トレイルは、「歩くことは、自然と最も素直につながる方法のひとつ」という大切なことを教えてくれる、日本で初めて本格的に整備されたロングトレイルです。全長110kmにおよぶ道を歩けば、ブナの森の静けさや雪解け水の流れに、私たちが自然の一部であることを実感できます。
しかし、私たちが安心して歩けるその道は、誰によって支えられているのでしょうか。
トレイル整備に励むボランティア、持続的な道の管理運用について模索する運営スタッフ、そして海外トレイルからの学びや国内の仲間たちとの連携など、信越トレイルは、自然体験の裏側にある人々の努力と挑戦によって成り立っています。
今回は、運営組織である『NPO法人信越トレイルクラブ』の事務局スタッフのお一人である、佐藤有希さん(以下、佐藤)にお話を伺いました。
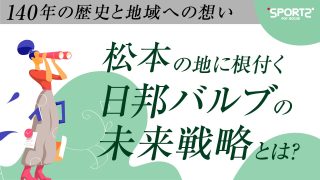
雨のブナの森に魅了され、信越トレイルクラブへ
ーー 佐藤さんはもともと自然の中を歩いたり、山登りをすることに興味があったのですか?
佐藤)小さい頃から、父に連れられて山登りをしていました。大人になり山から離れていましたが、もう1回山登りをしてみようと思った出来事が、3.11の東日本大震災です。震災当時は東京で働いていましたが、父の故郷が岩手だったこともあり、何かできることはないかと被災地ボランティアに参加しました。初めてのテント暮らしで13泊を経験した後、使い道のなくなったテントが手元に残り、これを使って何かできないかと考えて再開したのが山登りでした。
ーー 3.11がきっかけで山登りを再開されたのですね。そこから信越トレイルに興味を持ったきっかけを教えてください。
佐藤)きっかけはNHKのドキュメンタリー番組で特集されていたアメリカのアパラチアントレイルを見たことです。大人になって山登りを楽しんでいたときに、ふと番組のことを思い出していろいろと調べていくうちに、信越トレイルにたどりつきました。そのときに1番影響を受けたのは、日本のロングトレイル界の先駆者である加藤則芳さんの著書を読んだことですね。
ーー トレイルへの興味を刺激されたのは、先駆者の書かれた1冊の本との出会いなのですね。特に影響を受けた部分は、どんなところだったのでしょうか?
佐藤)「人間本来自然たるべきもの」という言葉です。人は自然の一部なんだ、と理解しています。旅のスタイルの1つである「長距離トレイル」や「長距離ハイキング」の冒険感にも惹かれました。
ちなみに、日本初の本格的ロングトレイルと呼ばれる「信越トレイル」は、もともと国の調査事業としてスタートした長野県と新潟県の広域連携プロジェクトなんです。当時の飯山市長・小山邦武氏の主導によるグリーンツーリズムの取り組みの流れも重なり、「里山を含めた地域の自然環境の保全と利活用」という考えをベースに、信越トレイルの構想がまとまりました。
そこに加藤則芳さんが加わったことで、アメリカのトレイルカルチャーや彼自身の持つフィロソフィーがエッセンスとして注入され、この道は生まれました。加藤さんに導かれるかたちで、管理運営の手法をアパラチアントレイルに学んだ、というくだりにも、心を動かされました。

ーー 実際に初めて「信越トレイル」を歩かれて、いろいろなことを感じられたと思います。
佐藤)初めて信越トレイルを歩いたのは2016年です。当時は全長80キロだったトレイルを4泊5日で歩くという未知の体験でしたが、「行ってみよう」と思いチャレンジしました。信越トレイルは地形的に雲が湧きやすく、雨が多いところです。初めてのスルーハイクも天気は大荒れで、一般的な登山の感覚だと最悪の条件でした。でも、逆にそれがすごく良かったんです。
ーー 最悪の天気だったのにそれが良かったということは、特別な何かがあったのですか?
佐藤)信越トレイルの見どころの1つに「ブナの森」があるのですが、雨が降っている方が雰囲気が出て、森のミスティな感じがすごく魅力的でした。森が生きている感覚をダイレクトに感じられて、とても楽しかったです。5日間という短い期間でしたが、「歩いて、食べて、眠るだけ」というシンプルな生活が、自分に合っていてしっくりときました。今やるべきことに集中できる感覚が、とても心地良かったです。
信越トレイルに何度か通ってイベントなどに参加しているうちに、信越トレイルクラブの事務局の人やガイドさんたちなど、親しい人が増えていきました。自然も関わっている人たちも魅力的で、2018年の12月に飯山市に移住し、その翌年2019年4月から地域おこし協力隊として信越トレイルクラブの事務局で働き始めました。
自然の表情は一期一会、豪雪地帯ならではの魅力
ーー 歩く側だけでなく運営側としても関わり始めてから、あらためて気づいた魅力はありますか?
佐藤)信越トレイルに関わる皆さんが、それぞれに熱意や想いを持っていることです。歩きに来てくれるハイカーや整備ボランティアの皆さん、地元のお宿さんやガイドさん、事務局メンバーも含め、1人ひとりが本当にアツいなと感じます。
ボランティアの皆さんには、主に草刈りをお願いしているのですが、中にはトレイル整備に夢中になってくださる方もいます。自分で草刈機の安全講習を受けてきて「機械を使えるようになったので使わせてください」という方もいました。
ーー 自主的に草刈機の安全講習を受講するくらい熱意のあるボランティアの方がいるのは、とても嬉しいですよね。
佐藤)そうですね。毎年、シーズンを通してボランティアを募集しています。週2~3回のペースで整備イベントをやっているのですが、毎回誰かしら参加してくれ、ひとりもいないということはほぼ皆無です。新しい人たちも増えてきていますし、リピーターの方々や遠方からはるばる来てくださる方も多くいることはとても有難いですね。
皆さん「楽しかった、また来たいです」という風に言ってくださるので、嬉しくなります。信越トレイルクラブとしても、修行のようにシリアスに整備をするというよりは、みんなで楽しくワイワイやろうということを基本コンセプトとして大切にしています。

ーー 関わる「人」の魅力が素敵ですね。「トレイル」としての魅力はどんなところでしょうか?
佐藤)季節ごとに自然のさまざまな景観を目にしたり、変化を感じることができます。その年の気候によってトレイルの環境も変わります。例えば雪が少なかった年の次のシーズンは水場が枯れてしまうこともあり、それが旅のアクセントになります。歩くルートは同じですが、時期や年によって違った状況を味わえるので、この表情の違い、一期一会の体験が、信越トレイルの大きな魅力の1つだと思います。
また、先ほどお話しさせていただいた「雨のブナの森」も魅力的なのですが、豪雪地帯なので、歩けるのが1年の半分というところも、信越トレイルの特徴です。残りの半分は雪に埋まっているので、シーズン中は思いっきり楽しもうという気持ちになります。一歩一歩に価値が凝縮される感じですね。
ーー その時々の自然の表情を楽しめるのも、信越トレイルの魅力なんですね。自然の表情をできるだけそのまま残すために、整備面でのこだわりや工夫を教えてください。
佐藤)人ひとりが通れる最低限の道幅、いわゆる木こり道のようなトレイル、というのが、整備する上での考え方です。草刈り機や小型のチェーンソーは使いますが、重機は入れません。ハンドメイドな整備を行うことがモットーですね。これは、加藤則芳さんの言葉である「爪でひっかいたような1本のトレイル」をコンセプトにしているためです。
また、基本的に人工物は極力据えないようにしています。環境保全の面もありますが、雪の影響で必ず壊れてしまうので。例えば、急な斜面には階段をつけるのではなく、スコップとかけやでステップを刻む。ぬかるみの足場もできるだけその環境にある倒木や石などの材を集めて配置することで、ダメージを受けても容易に補修できるようにしています。
ーー トレイルランは開催されていないのでしょうか?
佐藤)「トレイル=トレイルラン」と認識される方も一定数いて、信越トレイルも一般の方から「トレイルランの大会ですか?」と聞かれることがよくあります。一時に大勢が走るトレイルランの大会は、路面や周囲の植生の保全に影響を与えてしまう可能性があるため、信越トレイルでは開催していません。ですので、歩くための道として整備しているということを伝えています。

全長3,500kmのアメリカ三大トレイル・アパラチアントレイルから学んだ運営の知恵
ーー アメリカ三大トレイルの1つと呼ばれるアパラチアントレイルと協定を結んでいるというお話を伺いました。
佐藤)2023年にアパラチアントレイルコンサーバンシー(ATC)と友好トレイル協定を結びました。信越トレイルはアパラチアントレイルをモデルに作られたので、彼らと協定を結び、協力関係になれたのはとても良い機会でしたし、ハッピーな出来事でした。
協定を結んだあとは、アパラチアントレイルを整備している各地域のトレイルクラブの皆さんが信越トレイルに来てくれて、一緒に歩いたり整備をやったりと人的交流が生まれています。気軽に行き来できる距離ではないですが、今やオンラインでいくらでもやり取りできるので、彼らから見聞きする新しい情報や技術、私たちにとっては目からウロコな知識など、勉強になることがたくさんあります。
「アパラチアントレイルは100年の歴史があるが、これまでにいろいろな試行錯誤を繰り返してきた。たどり着いた答えを100年前に先に知っていれば、私たちは今進めている景観保全の取り組みや啓発活動をもっと早くに始められたはずだと考えている。だから、100年間の蓄積をみなさんに共有することで、日本のトレイルが良い方向にスムーズに発展していってほしい」と言われていたことはとても印象的でしたね。

ーー 100年間で積み上げてきた情報は、とても貴重だと思います。いただいた情報をもとに、どんなことに取り組まれていますか?
佐藤)例えば雪の影響などで、場所によっては急斜面の土が削られてしまい滑りやすかったり、ルート上にぬかるみができてしまう箇所があったりするのですが、トレイルの路面に水が溜まらない整備方法を伝授していただき今年から実践しています。
整備以外にも、財源確保のためにドネーションで遠慮なく声をあげるということを教えていただきました。米国はキリスト教の影響もあり、寄付文化や施しを与えるというのが、もともとの観念としてあります。日本には自国にあったやり方があると思うので模索中です。
ーー 財源確保はやはり重要な課題ですよね。
佐藤)そうですね。もちろん整備にも費用がかかりますし、信越トレイルを維持管理するためには運営スタッフも欠かせません。持続的にやっていくためにも、財政面の取り組みは必要だと強く感じています。我々はNPO法人ですので、会員の皆さんから納入いただく会費が運営資金の基盤です。ひとりでも多くの方が信越トレイルのサポーターになっていただけるよう、今後も発信を続けていかなければなりません。また、受益者負担という観点から、歩くハイカーの皆さんには「トレイル整備協力金」の寄付をお願いしています。
さまざまな方が想いを持って関わってくださっていますし、信越トレイルは日本のロングトレイルの先駆けとしてベンチマークされている存在でもあるので、トライアンドエラーを繰り返しながらでも走り続ける必要があると思っています。加藤則芳さんもきっと見守ってくださっているはずなので、足元を見ながらしっかりやっていきたいですね。
信越トレイルのこれから、人と地域を繋ぐ役割
ーー 信越トレイルを今後どのように展開していきたいと考えていますか?
佐藤)加藤則芳さんが生前に言われていた「信越国境すべてを貫く壮大な信越トレイル」というのが、常に我々の中にあります。2021年に長野駅を起点に開通した総延長86kmの「あまとみトレイル」と信越トレイルは、斑尾山頂で接続しています。全部繋げて歩くと200km、ロングトレイルとして楽しむのにわりと良い感じの距離です。今後は雨飾山方面への延伸も念頭に、同じ地域のトレイルとして一緒に気運を高め、トレイル文化を根付かせていきたいです。

ーー県境を越えて繋がる道ができると、人の交流も生まれそうですね。
佐藤)はい、実際に信越トレイルができたことで生まれた交流はいくつもあります。最近で言うと、新潟側と長野側でかつて交易が盛んに行われていた峠道(信越トレイルのアプローチトレイル)を使って、お互いの集落を行き来してみようというイベントを、昨年地元の方々が開催して、たくさんの参加者が新潟側から長野側へ歩いて来てくれました。
また別のところでは、信越トレイルが通る集落のうちのひとつ、全3世帯という本当に小さな集落で、地元の方がハイカーに立ち寄ってほしいと空き家の古民家を買ってリノベーションしたカフェが、もうすぐ開店します。そういった小さな盛り上がりが今後もっと増えていってほしいですし、我々としても地域の皆さんと一緒に育んでいきたいですね。
ーートレイルには自然を歩く以外にも大きな可能性があると感じました。
佐藤)信越・北信エリアに限らず、日本各地にトレイルが増えてきていて、それぞれがみんな想いを持って運営を行っています。彼らはいわば「トレイル仲間」。その存在は本当に心強いですし、一緒に日本のロングトレイルシーンを盛り上げていける状況が整い始めたのが何より嬉しいです。
「同じ想いを持つ仲間が周りにいる」ということが、私がこの活動を続けている一番の力の源ですね。
ーー自然を感じ、一歩一歩を味わいながら歩くロングトレイル。信越トレイルは、ただの登山道ではなく、地域と人をつなぎ、未来へ受け継がれていく“道”です。雨のブナ林も、雪解けの小川も、歩くたびに表情を変えながら、訪れる人に「人は自然の一部」であることを静かに語りかけています。
<参考:外部リンク>
信越トレイルの誕生秘話
信越トレイル整備協力金のおねがい


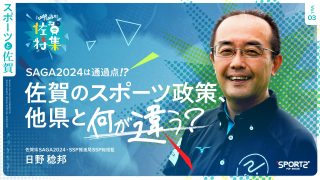

ー